「育児休暇って、正直いつ取るのが一番いいんだろう?」初めての子どもを授かった時、私と妻も同じ疑問を抱えていました。周りのパパ友に聞いたり、会社の育児制度を調べたりと、手探りで情報を集める日々でしたね。
今回は私自身の育児休暇取得経験をもとに、これから育児休暇を検討している皆さんに
おすすめの取得時期や、知っておくと得する経済的なメリット
について、詳しくお伝えしたいと思います。
最後まで読んでみてください。
出産直後の「ゴールデン期間」を最大限に活かす:リモートワークと実家滞在の組み合わせ
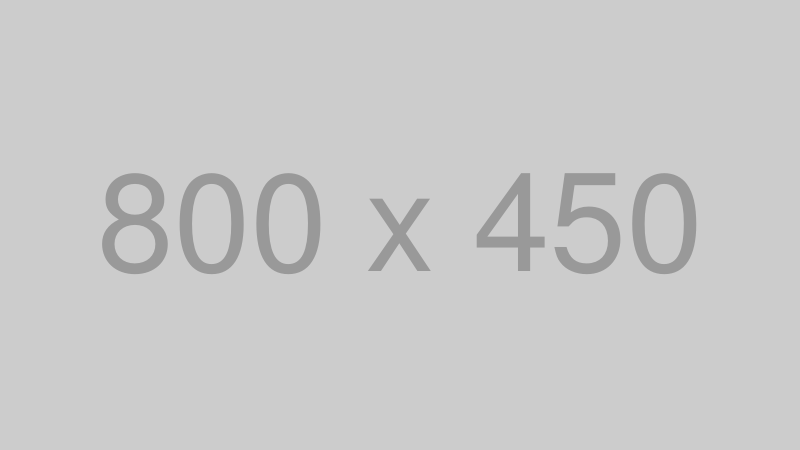
私の場合、下記が当てはまりました。
- 仕事がリモートワーク可能だったこと
- 出産予定日が5月末
- ゴールデンウィーク明けから6月中旬までの期間を、妻の実家で過ごす
出産直後、妻はまだ入院中だったので退院までの5日間、妻の実家でお世話になりました。
義両親は働いているので私が毎日夕食を作りました。正直なところ最初は少し緊張しました。でも、これは私にとって非常に良い経験になりました。義理の息子としてさらに受け入れられた気がします。
そして退院。出産直後のママの体は、想像以上にデリケートです。出産の疲れはもちろん、ホルモンバランスの変化で精神的にも不安定になりがちです。加えて、慣れない新生児のお世話は、まさに24時間体制の体力勝負ですよね。そんな中で、家事のすべてを妻に任せるのは酷です。実家で過ごすことで、義母が食事の準備や洗濯などを手伝ってくれたのは、妻にとって大きな安心材料になったと思います。私も、精神的な面でサポートを受けられたことで、余裕を持って育児と仕事に向き合えました。
この時期、私は実家からリモートで仕事を続けました。会社への通勤時間がゼロになる分、その時間を育児や家事に充てられたのは、本当に効率的でしたね。例えば、午前中は仕事に集中して、お昼休憩中はミルクをあげたり、赤ちゃんのおむつを替えたり。夕食の準備を少し手伝ったり、お風呂に入れる練習をしたりと、積極的に育児に参加できました。赤ちゃんの寝顔を見ながら仕事をするのは、これまでのビジネスライフでは経験したことのない、不思議で温かい時間でした。
妻の実家を出る1週間前には、私だけ先に自宅に戻りました。これは、本格的な育児生活を自宅で始めるための準備期間です。妻と赤ちゃんが快適に過ごせるよう、念入りに掃除をしたり、ベビー用品の配置を整えたり。この準備期間があったおかげで、自宅に戻ってきてからの生活もスムーズにスタートできました。このあたりの具体的な準備については、また別の機会に詳しくお話ししますね。
実際の社会保険料免除の内容
実際の給与明細を元に2つの内容関して説明させていただきます。
- 育児休暇の大きな味方:社会保険料免除の恩恵を最大限に活用する
- 賞与(ボーナス)にかかる社会保険料も免除に!
#01:育児休暇の大きな味方:社会保険料免除の恩恵を最大限に活用する
育児休暇を検討する上で、ぜひ知っておいてほしいのが「社会保険料の免除制度」です。私はこの制度を最大限に活用するために、育児休暇の取得日を調整しました。具体的には、私は6月30日(月)から育児休暇を取得したんです。最終日有給休暇ではなく育児休暇を選択したのは、この社会保険料免除のメリットが非常に大きかったからです。
少し具体的な話をしましょう。当時の私の月収は35万円でした。単純に1日あたりの給与を計算すると、およそ15,000円になります。もし育児休暇を「欠勤」扱いとして取得した場合、その日の給与は発生しません。しかし、育児休暇中は健康保険料と厚生年金保険料といった社会保険料が免除されます。私の場合は、ひと月あたりの社会保険料が約25,000円でした。
つまり、たった1日育児休暇を取得して給与が15,000円減ったとしても、社会保険料の免除額が25,000円あるため、差し引きで10,000円のプラスになる計算です。これは、金銭的な面から見ても、育児休暇取得を強く後押しする要因になりました。
#02:賞与(ボーナス)にかかる社会保険料も免除に!
私の場合は、ちょうど6月に賞与が支給される月でもあったため、この賞与にかかる社会保険料も免除の対象となりました。 賞与から差し引かれる社会保険料は決して少なくありません。これが免除されることで、育児休暇中の経済的なゆとりがさらに大きくなったのを覚えています。賞与の支給月と育児休暇の開始時期が重なる場合は、ぜひこの社会保険料免除の恩恵を意識してみてください。
この社会保険料免除制度は、2022年10月の法改正でさらに柔軟になりました。以前は「月末まで育児休業を取得していること」が基本的な免除要件でしたが、現在はそれに加えて「同月内に14日以上(土日祝日含む)の育児休業を取得した場合も、その月の社会保険料が免除される」という新しいルールが加わりました。これにより、たとえ月末まで育児休暇を取れなくても、数週間程度の短い期間でも社会保険料免除の恩恵を受けられるようになったんです。
ただし、賞与にかかる社会保険料の免除要件は厳しくなっています。2022年10月以降は、「賞与月の末日を含んだ連続した1ヶ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、その賞与にかかる社会保険料が免除される」ことになりました。短期間の育児休暇では、賞与にかかる社会保険料は免除されなくなったので、この点は注意が必要です。私のケースは、法改正前の取得だったため、1日でも免除の対象となりましたが、現在はより長期の育休が必要となる点にご留意ください。
また、社会保険料は月単位で計算されますが、会社の給与計算の締め日と支給日によっては、実際の控除月と免除月がずれることがあります。例えば、会社の給与計算が「当月25日締め、翌月10日払い」の場合、7月分の社会保険料は8月支給の給与から控除されるといった形になります。育児休暇を取得する際は、ご自身の会社の給与計算のサイクルを確認し、いつから手取り額に反映されるのかを把握しておくと、資金計画を立てやすくなります。
育児休暇は家族の「チーム力」を高める時間
育児休暇は、ただ赤ちゃんとの時間を過ごすだけではありません。それは、夫婦の絆を深め、家族としての「チーム力」を高める絶好の機会です。私の場合、妻の実家で過ごした期間も、自宅に戻ってきてからの育児休暇も、夫婦で協力して育児に取り組むことで、互いの役割や連携プレーが自然と生まれていきました。
初めての育児は、分からないことだらけで、不安も大きいものです。「ミルクの量はこれでいいのかな?」「おむつ替えのタイミングは?」「この泣き方はどういう意味?」といった疑問が次々に湧いてきます。そんな時、夫婦で一緒に悩み、調べ、考え、そして小さな成長を喜び合う時間は、何物にも代えがたい貴重な経験になります。
育児休暇を取得することで、パパも育児の「当事者」意識を強く持てるようになります。新生児期の夜中の授乳や、突然の体調不良など、大変な局面ももちろんあります。しかし、それを夫婦で乗り越えることで、互いへの信頼感や感謝の気持ちが深まり、家族としての絆がより一層強固になることを実感しました。これは、育児休業給付金や社会保険料免除といった経済的なメリット以上に、かけがえのない財産となるでしょう。
まとめ:あなたと家族にとって最適な育児休暇を
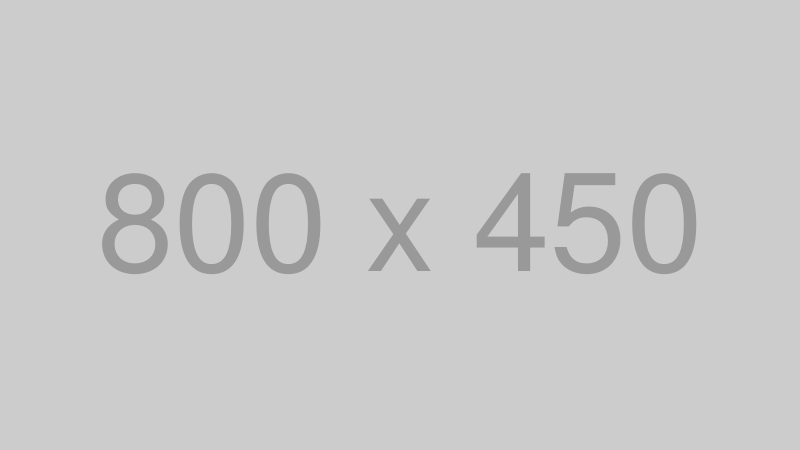
育児休暇の取得は、各家庭の状況や会社の制度、そして何よりも夫婦の価値観によって様々です。しかし、少しでも育児休暇に興味があるなら、まずは情報収集を始めることを強くおすすめします。
- 会社の育児制度を確認する: 育児休業規程や、上司、人事担当者と具体的な取得期間や手続きについて相談しましょう。
- 社会保険料免除の適用条件を理解する: 2022年10月の法改正による変更点を踏まえ、いつ休むのが最も経済的なメリットが大きいかを検討しましょう。特に、賞与支給月と育児休暇の期間が重なる場合の社会保険料免除の条件は、法改正で厳しくなっているため、事前にしっかり確認してくださいね。
- 夫婦でじっくり話し合う: 育児休暇の目的、期間、過ごし方について、パートナーと十分に話し合い、共通認識を持つことが成功の鍵です。
育児休暇は、人生の中で限られた、貴重な時間です。この期間をどう過ごすかは、その後の家族関係や子どもの成長にも大きな影響を与えます。経済的なメリットを最大限に活かしつつ、あなたとあなたの家族にとって、最善の選択肢が見つかることを心から願っています。
育児休暇の取得を検討されている皆さんにとって、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
今回のブログでは新生活の準備と経済的メリットに関して2つの説明をさせていただきました。
- 出産直後の「ゴールデン期間」を最大限に活かす:リモートワークと実家滞在の組み合わせ
- 実際の社会保険料免除の内容
引き続きよろしくお願いいたします。
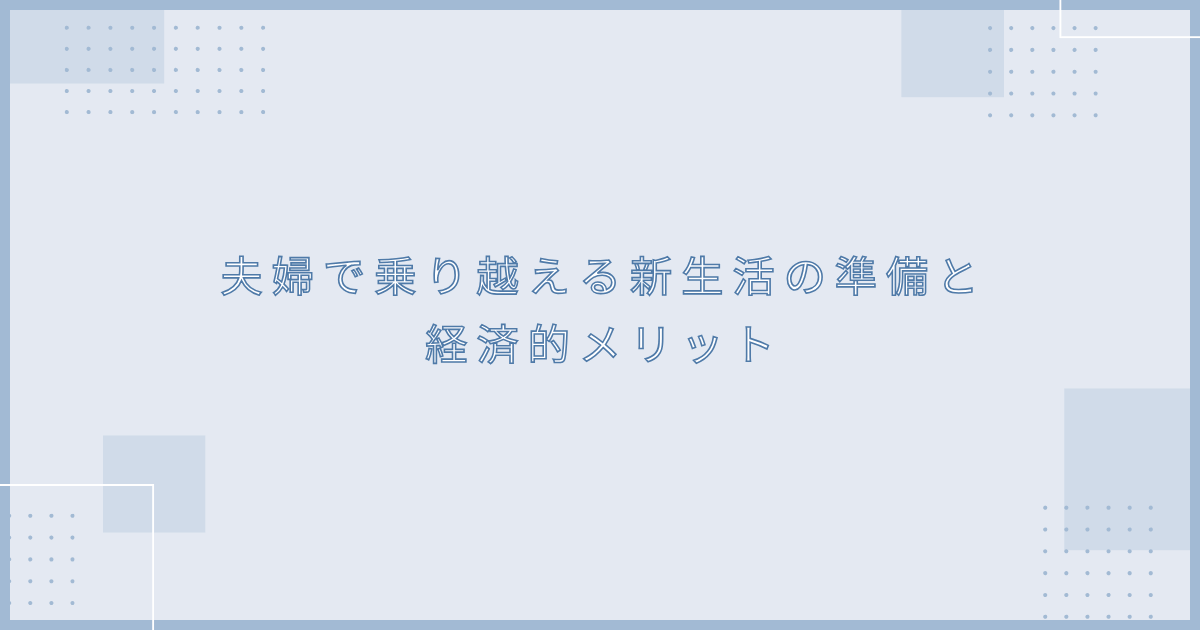
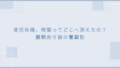
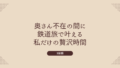
コメント